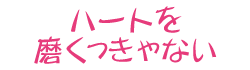 |
いつものようにバッティングセンターで軽く汗を流すと、東雄平は併設された喫茶店の扉を開けた。
閉店時間に近いせいか他の客の姿はなく、カウンターの中にはエプロン姿の一葉と紅葉がいるだけだ。紅葉がバッティングセンターで父親の手伝いをしている姿は何度か見かけたことがあったが、喫茶の方の、しかもカウンターの中にいるのを見るのは初めてだった。
普段は青葉が使っているエプロンを付け、ポットを載せたコンロの火をじっと見つめている。しかし入ってきた東に気付くと、紅葉はすぐさま顔を上げた。
「ゆーへー、いらっしゃい」
「紅葉、あんたねぇ」
年上の人間を呼び捨てにするとは何事だと一葉は眉をひそめたが、紅葉はどこ吹く風で笑みを浮かべている。
「構いませんよ」
いつも通り一葉に軽く会釈して、東はカウンターの席に座った。
一葉と、東の兄の純平が結婚して近いうちに兄妹になる間柄だから、気にする必要はない。そう告げる東に、紅葉が神妙な顔をした。
「お兄ちゃんって呼んだ方がいい?」
「好きにしろ」
背負っていた鞄をカウンターに立てかけ、東は興味なさげに答える。東が樹多村家に居候してから、月島家の歳の離れたこの姉妹とは、バッティングセンターの常連としての付き合いはあった。
しかし義理とはいえ、本当に姉と妹になるというのにはまだまだ実感が沸かないし、なんとなく気恥ずかしいものがある。
「それで、お前は何をしているんだ?」
話題を逸らすようにコーヒーを注文してカウンターに向き直ると、紅葉はにぱっと笑みを浮かべた。
「練習」
「練習?」
「一葉お姉ちゃんに、美味しいコーヒーの入れ方を教わってんの」
何故、と眉を寄せる東に、紅葉は言葉を続けた。
「暫くは一葉お姉ちゃんがいるけどお嫁に行っちゃうし、アオちゃんは戦力にならない上に、光の所にお嫁に行っちゃうからね」
「居候の従兄弟はどうした?」
「旅に出ちゃった」
紅葉によると、東たちが甲子園行きを決めた翌々日には、書き置きだけ残して居なくなっていたらしい。
「それでお前か」
東の言葉にえっへん、と胸を反らす紅葉に、一葉は小さく息を吐いた。
「ほら、お湯が沸いてから、豆を煎れるのよ」
カウンターの向こう側にはコーヒードリップが準備されていて、くるりとフィルターが巻かれている。
火にかけたポットが水蒸気を立て始めると、紅葉はコンンロの火を止めて、後方の棚へ身体を向けた。中学生になったとはいえ、背が低めの紅葉には辛いのか、つま先立ちになっている。削ったコーヒー豆の袋を棚から取り出すと、スプーン3杯をフィルターの上に載せ、ポットを両手で持った。
「ゆっくり、こぼれないように注意して」
一葉の言葉に従い、時々手を止めながら円を描くようにして湯を注いでいく。
「一杯分はここのメモリで、二杯分だとココね」
一葉が指す印まで黒い液体が溜まると、紅葉はポットをコンロの上に戻し、両手を離して一息吐いた。
「残りのお湯で、カップを温めるのよ」
しかし休む間もなく一葉の説明が続き、真剣な眼差しで作業を進めていく。棚からコーヒー皿とカップを2セット取り出し、ポットのお湯をカップに注いでいく。
コーヒーの抽出が終わるとすぐさまフィルターを外し、ゴミ箱に捨てた。そしてカップのお湯を捨て、コーヒーを注いでいく。
「できたぁ!」
どうにか二杯分のコーヒーを注ぎ終わり、それぞれ皿の上に置くと、紅葉は万歳をするように両手を上げた。
一葉のスムーズな動作に比べると、時間が倍近く掛かっており、まだまだ危なっかしい。
コーヒーカップを載せた小皿を両手で持ち、そろそろとカウンターに置くと、紅葉はすませた表情を浮かべて東に差し出した。
「お待たせしました」
紅葉の視線を感じながら、東はカップを口元に運んだ。
「どう?」
恐る恐る尋ねる紅葉に、東は一口啜った後、カップを皿に戻し、紅葉へと視線を向けた。
「いつも通りだな」
薄くもなく濃くもないと感想を述べると、紅葉は両拳を握り、「よし」と小さくガッツポーズした。その傍らでは、一葉がもう一個入れたカップに口を付けて味見をしている。
「うん、あとは手際よく出来れば合格かな」
小さく頷く一葉に、紅葉は両目を輝かせた。その様子を微笑ましく眺めながら、東は再びカップを口元へ運ぶ。
そこでふと気付いて、東はカップを置いた。
「これからはナポリタンもお前が作るのか?」
そう尋ねると、紅葉は大きく息を吐いて、肩を竦めてみせた。
「高校生になるまでは料理は駄目だってサ」
「だから、なるべく父さんにコッチに出て貰うつもり」
つまらなさそうに唇を尖らせる紅葉に、一葉は苦笑を浮かべた。
「でもね、家ではちゃんと料理を教わっているんだよ」
結婚後は、店の手伝いには来ても家からは出ていくので、台所など一葉が預かっていた分の大半を、今度は紅葉が引き継ぐらしい。
「月島は?」
東の言葉に、紅葉は困ったように眉を寄せた。
「アオちゃんはホラ、台所限定でドジっ子だから」
紅葉の言葉に、一葉も諦めたように息を吐いた。
幸か不幸か東も居合わせたことがあるが、青葉は料理に関してだけは、どうしようもなく不器用だった。
まず作るまでに調理機器や材料をひっくり返し、どうにか出来上がってもイビツな形状をしている。その上というか、当然というべきか、味まで奇妙で本当にどうしようもない物体が出来上がるのだ。
「でも良かったよね。アオちゃん、アレでもお嫁の貰い手があるんだもん」
ニコニコと笑みを浮かべる紅葉に、東も少しだけ眉をゆるめた。
しかし、一葉は東の表情に困ったように柳眉を寄せると、「アンタは一言多いのよ」と紅葉を軽く小突いた。そして点灯している看板の電源を切ると、カウンターから出て、喫茶店の入り口にぶら下がっている「営業中」の札をひっくり返す。
「ちょっと家の方見てくるから、片付けお願いね」
そう言い残すと、一葉はカウンター奥の扉へと消えていった。その姿を見送って、紅葉は東へと向き直る。
「ゆーへーってアオちゃん好きだったの?」
「あぁ」
さらりと認める東に、紅葉は大きく頷いた。
「振られちゃったね」
「お互いにな」
「おや」
元々丸い紅葉の両目が、さらに大きく見開かれた。
「……知ってた?」
「本人はさておき、第三者から見れば分かりやすかったと思うが」
「ですよねー」
コーヒーを啜る東に、紅葉は小さく頷いている。
「でもね、ホントに光がお兄さんになってくれるなら、それでもいいかなって」
そう言いながら、紅葉は空になったサーバーとドリッパーを流しに下ろし、水を注いだ。泡立てたスポンジで洗っていくのを眺めながら、東は琥珀色の液体を飲み進めていく。
「その前に、兄貴が二人も出来るな」
「ふむ」
カップを置いた東がぼそりと呟くと、紅葉は頷き返した。
「クールでカッコいい兄が出来るのは悪くないね」
「だろう?」
したり顔で再びコーヒーを啜る東に、紅葉は天井を見上げた。
「愉快なのと、カッコいいのと、優しいお兄さんかぁ」
そして再び視線を落とし、蛇口を捻った。
「光はね、いつも私の話を聞いてくれたんだァ」
付いた泡を水で注ぎ落としながら、紅葉は俯いたまま言葉を続けた。
「光とのキャッチボールだって、私の方がアオちゃんよりも先に、ずっと一緒にやってたんだよ」
淡々とした口調で「もうちょっと早く生まれたかったなぁ」と軽くため息を吐く紅葉に、東は無言で耳を傾けた。
「まぁ、あんな感じであの二人を見るのも好きなんだけどね」
そう言うと、紅葉は蛇口を閉めた。流し近くに下げたタオルで両手を拭く。それを目で追いながら、東はぽつりと呟いた。
「奇遇だな」
自分もそうだと頷き、空にしたコーヒーカップを皿ごと差し出した。紅葉はそれを両手で受け取ると、流しに移し、スポンジで擦っていく。
東は静かに立ち上がると、慰めるように、紅葉の頭を軽く叩いた。
突然のことに紅葉は少しだけ目を丸くしたが、無表情に近い東を見上げて、口元を綻ばせた。
「そういう優しさも悪くないけど、光みたいにちゃんと言葉にしないとモテないぞ」
冗談めかした紅葉の口調に、東は紅葉の頭上に手を置いたまま、さらりと返す。
「これ以上はモテる必要はないから、問題ない」
「言いますなァ」
そして手を引っ込めると、東は、傍らに置いた野球道具を手に取った。
「カウンターに立てるようになったら、光とナポリタン喰いに来てやるよ」
「ホント?!」
東の言葉に、紅葉は目を輝かせた。
「アオちゃんより絶対まともだよ」
「そうでないと困る」
笑う紅葉に、東は苦笑を返した。
<了>
閉店時間に近いせいか他の客の姿はなく、カウンターの中にはエプロン姿の一葉と紅葉がいるだけだ。紅葉がバッティングセンターで父親の手伝いをしている姿は何度か見かけたことがあったが、喫茶の方の、しかもカウンターの中にいるのを見るのは初めてだった。
普段は青葉が使っているエプロンを付け、ポットを載せたコンロの火をじっと見つめている。しかし入ってきた東に気付くと、紅葉はすぐさま顔を上げた。
「ゆーへー、いらっしゃい」
「紅葉、あんたねぇ」
年上の人間を呼び捨てにするとは何事だと一葉は眉をひそめたが、紅葉はどこ吹く風で笑みを浮かべている。
「構いませんよ」
いつも通り一葉に軽く会釈して、東はカウンターの席に座った。
一葉と、東の兄の純平が結婚して近いうちに兄妹になる間柄だから、気にする必要はない。そう告げる東に、紅葉が神妙な顔をした。
「お兄ちゃんって呼んだ方がいい?」
「好きにしろ」
背負っていた鞄をカウンターに立てかけ、東は興味なさげに答える。東が樹多村家に居候してから、月島家の歳の離れたこの姉妹とは、バッティングセンターの常連としての付き合いはあった。
しかし義理とはいえ、本当に姉と妹になるというのにはまだまだ実感が沸かないし、なんとなく気恥ずかしいものがある。
「それで、お前は何をしているんだ?」
話題を逸らすようにコーヒーを注文してカウンターに向き直ると、紅葉はにぱっと笑みを浮かべた。
「練習」
「練習?」
「一葉お姉ちゃんに、美味しいコーヒーの入れ方を教わってんの」
何故、と眉を寄せる東に、紅葉は言葉を続けた。
「暫くは一葉お姉ちゃんがいるけどお嫁に行っちゃうし、アオちゃんは戦力にならない上に、光の所にお嫁に行っちゃうからね」
「居候の従兄弟はどうした?」
「旅に出ちゃった」
紅葉によると、東たちが甲子園行きを決めた翌々日には、書き置きだけ残して居なくなっていたらしい。
「それでお前か」
東の言葉にえっへん、と胸を反らす紅葉に、一葉は小さく息を吐いた。
「ほら、お湯が沸いてから、豆を煎れるのよ」
カウンターの向こう側にはコーヒードリップが準備されていて、くるりとフィルターが巻かれている。
火にかけたポットが水蒸気を立て始めると、紅葉はコンンロの火を止めて、後方の棚へ身体を向けた。中学生になったとはいえ、背が低めの紅葉には辛いのか、つま先立ちになっている。削ったコーヒー豆の袋を棚から取り出すと、スプーン3杯をフィルターの上に載せ、ポットを両手で持った。
「ゆっくり、こぼれないように注意して」
一葉の言葉に従い、時々手を止めながら円を描くようにして湯を注いでいく。
「一杯分はここのメモリで、二杯分だとココね」
一葉が指す印まで黒い液体が溜まると、紅葉はポットをコンロの上に戻し、両手を離して一息吐いた。
「残りのお湯で、カップを温めるのよ」
しかし休む間もなく一葉の説明が続き、真剣な眼差しで作業を進めていく。棚からコーヒー皿とカップを2セット取り出し、ポットのお湯をカップに注いでいく。
コーヒーの抽出が終わるとすぐさまフィルターを外し、ゴミ箱に捨てた。そしてカップのお湯を捨て、コーヒーを注いでいく。
「できたぁ!」
どうにか二杯分のコーヒーを注ぎ終わり、それぞれ皿の上に置くと、紅葉は万歳をするように両手を上げた。
一葉のスムーズな動作に比べると、時間が倍近く掛かっており、まだまだ危なっかしい。
コーヒーカップを載せた小皿を両手で持ち、そろそろとカウンターに置くと、紅葉はすませた表情を浮かべて東に差し出した。
「お待たせしました」
紅葉の視線を感じながら、東はカップを口元に運んだ。
「どう?」
恐る恐る尋ねる紅葉に、東は一口啜った後、カップを皿に戻し、紅葉へと視線を向けた。
「いつも通りだな」
薄くもなく濃くもないと感想を述べると、紅葉は両拳を握り、「よし」と小さくガッツポーズした。その傍らでは、一葉がもう一個入れたカップに口を付けて味見をしている。
「うん、あとは手際よく出来れば合格かな」
小さく頷く一葉に、紅葉は両目を輝かせた。その様子を微笑ましく眺めながら、東は再びカップを口元へ運ぶ。
そこでふと気付いて、東はカップを置いた。
「これからはナポリタンもお前が作るのか?」
そう尋ねると、紅葉は大きく息を吐いて、肩を竦めてみせた。
「高校生になるまでは料理は駄目だってサ」
「だから、なるべく父さんにコッチに出て貰うつもり」
つまらなさそうに唇を尖らせる紅葉に、一葉は苦笑を浮かべた。
「でもね、家ではちゃんと料理を教わっているんだよ」
結婚後は、店の手伝いには来ても家からは出ていくので、台所など一葉が預かっていた分の大半を、今度は紅葉が引き継ぐらしい。
「月島は?」
東の言葉に、紅葉は困ったように眉を寄せた。
「アオちゃんはホラ、台所限定でドジっ子だから」
紅葉の言葉に、一葉も諦めたように息を吐いた。
幸か不幸か東も居合わせたことがあるが、青葉は料理に関してだけは、どうしようもなく不器用だった。
まず作るまでに調理機器や材料をひっくり返し、どうにか出来上がってもイビツな形状をしている。その上というか、当然というべきか、味まで奇妙で本当にどうしようもない物体が出来上がるのだ。
「でも良かったよね。アオちゃん、アレでもお嫁の貰い手があるんだもん」
ニコニコと笑みを浮かべる紅葉に、東も少しだけ眉をゆるめた。
しかし、一葉は東の表情に困ったように柳眉を寄せると、「アンタは一言多いのよ」と紅葉を軽く小突いた。そして点灯している看板の電源を切ると、カウンターから出て、喫茶店の入り口にぶら下がっている「営業中」の札をひっくり返す。
「ちょっと家の方見てくるから、片付けお願いね」
そう言い残すと、一葉はカウンター奥の扉へと消えていった。その姿を見送って、紅葉は東へと向き直る。
「ゆーへーってアオちゃん好きだったの?」
「あぁ」
さらりと認める東に、紅葉は大きく頷いた。
「振られちゃったね」
「お互いにな」
「おや」
元々丸い紅葉の両目が、さらに大きく見開かれた。
「……知ってた?」
「本人はさておき、第三者から見れば分かりやすかったと思うが」
「ですよねー」
コーヒーを啜る東に、紅葉は小さく頷いている。
「でもね、ホントに光がお兄さんになってくれるなら、それでもいいかなって」
そう言いながら、紅葉は空になったサーバーとドリッパーを流しに下ろし、水を注いだ。泡立てたスポンジで洗っていくのを眺めながら、東は琥珀色の液体を飲み進めていく。
「その前に、兄貴が二人も出来るな」
「ふむ」
カップを置いた東がぼそりと呟くと、紅葉は頷き返した。
「クールでカッコいい兄が出来るのは悪くないね」
「だろう?」
したり顔で再びコーヒーを啜る東に、紅葉は天井を見上げた。
「愉快なのと、カッコいいのと、優しいお兄さんかぁ」
そして再び視線を落とし、蛇口を捻った。
「光はね、いつも私の話を聞いてくれたんだァ」
付いた泡を水で注ぎ落としながら、紅葉は俯いたまま言葉を続けた。
「光とのキャッチボールだって、私の方がアオちゃんよりも先に、ずっと一緒にやってたんだよ」
淡々とした口調で「もうちょっと早く生まれたかったなぁ」と軽くため息を吐く紅葉に、東は無言で耳を傾けた。
「まぁ、あんな感じであの二人を見るのも好きなんだけどね」
そう言うと、紅葉は蛇口を閉めた。流し近くに下げたタオルで両手を拭く。それを目で追いながら、東はぽつりと呟いた。
「奇遇だな」
自分もそうだと頷き、空にしたコーヒーカップを皿ごと差し出した。紅葉はそれを両手で受け取ると、流しに移し、スポンジで擦っていく。
東は静かに立ち上がると、慰めるように、紅葉の頭を軽く叩いた。
突然のことに紅葉は少しだけ目を丸くしたが、無表情に近い東を見上げて、口元を綻ばせた。
「そういう優しさも悪くないけど、光みたいにちゃんと言葉にしないとモテないぞ」
冗談めかした紅葉の口調に、東は紅葉の頭上に手を置いたまま、さらりと返す。
「これ以上はモテる必要はないから、問題ない」
「言いますなァ」
そして手を引っ込めると、東は、傍らに置いた野球道具を手に取った。
「カウンターに立てるようになったら、光とナポリタン喰いに来てやるよ」
「ホント?!」
東の言葉に、紅葉は目を輝かせた。
「アオちゃんより絶対まともだよ」
「そうでないと困る」
笑う紅葉に、東は苦笑を返した。
<了>
|
|